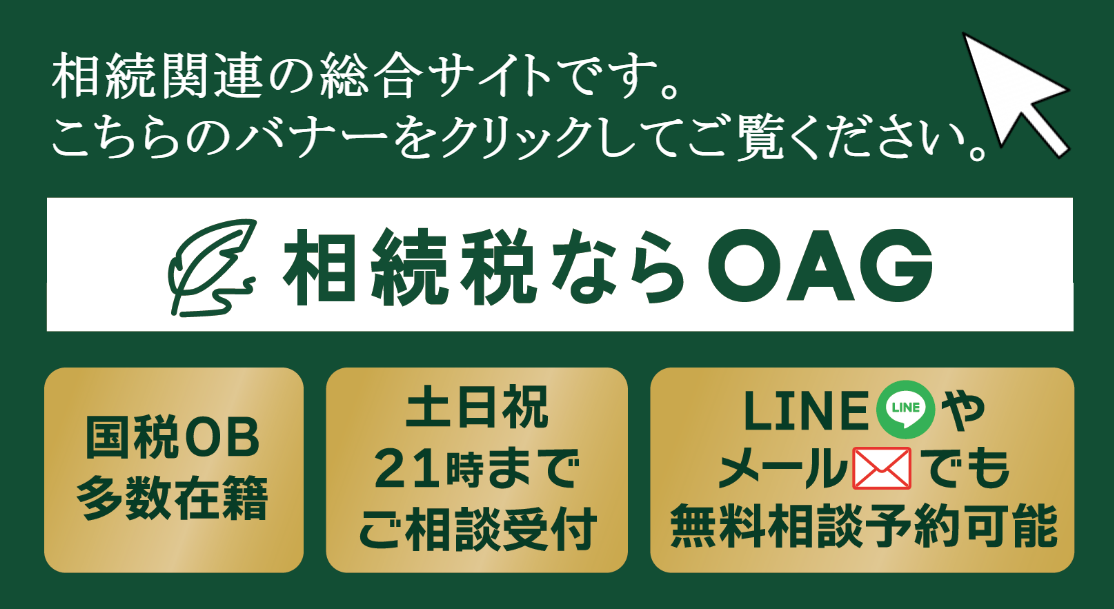個人向けサービス SERVICE 相続税申告 ~チーム相続~
相続税の申告、誰に依頼しても同じだと思っていませんか?
最良の相続には、豊富な知識と経験を持つ相続税専門税理士の知恵とノウハウが必要不可欠です。遺産相続手続き、相続税の申告サービスは、すべてお客さまからご相談をいただくところから始まります。はじめてのご相談から、ご契約のタイミング、アフターフォローまで、ご満足いただけるサービスを提供いたします。
SERVICE. 相続専門だから税務に自信あり
相続専門だから税務に自信ありへSERVICE. 相続の基本から安心サポート
相続の基本から安心サポートへSERVICE. 相続発生後のスケジュールからフォロー
相続発生後のスケジュールからフォローへSERVICE. 安心!事前見積もり
安心!事前見積もりへ
SERVICE POINT サービスの強み
- 年間実績1200件以上(グループ累計:10,000件以上)
- 創業35年以上の実績
- 相続専門書の執筆多数
- 事前にお見積り
相続
相談
の具体例
- 2024.04.19 不動産
- 《令和6年 地価公示価格発表》
- 2024.04.05 贈与税
- 《借地権の贈与(底地を子供が取得した場合)》
- 2024.03.22 相続税
- 《相続人が財産を取得しなかった場合に障害者控除は適用できる?》
 最新記事
最新記事
- 2024.01.15
- 相続税の更正の請求の書き方がわかる!請求書と次葉の記載と必要書類
- 2024.01.10
- 【旗竿地を相続する人必見】旗竿地の評価は3ステップで計算できる!
- 2024.01.09
- 【兄弟の相続放棄】相続放棄を兄弟一人だけ/まとめて手続きする方法